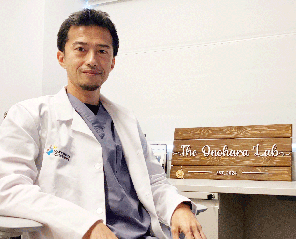1. 現在の活動について
2024年1月からオハイオ州コロンバスに移り、オハイオ州立大学医学部小児科のアシスタントプロフェッサーとして、ネーションワイド子ども病院の再生医療センターで研究室を運営しています。100%リサーチに専念しており、アメリカで臨床はしていません。
私のラボでは、前職のエモリー大学で行っていた研究を継承し、主に2つのプロジェクトを中心に進めています。
1つは、日本では心移植を受けることが難しいこともあり、心不全患者の選択肢が限られています。そこで、カテーテルを用いた低侵襲な治療法を開発しています。
発想の背景は、心不全悪化の要因とされている壁応力(wall stress)です。物理学のラプラスの法則で規定されているように、球形や円柱状の物体の壁にかかる張力は、その半径と圧力に正比例し、壁厚に反比例するという方程式があります。これらの数値のどれかを改善することで心不全の進行が抑制できると期待され、10数年前からさまざまなデバイスが開発されてきましたが、なかなか良い成果が出ませんでした。
心不全の新しい治療法として、マイトラクリップ(心臓弁の逆流を止めるクリップ状のデバイス)が世界的に普及していますが、クリニカルトライアル(臨床試験)の詳細を確認すると、心臓への負荷を軽減するために逆流を止めたとしても、心臓が大きく拡張している場合は、壁応力が高いままで心不全の進行を止められないことが分かりました。つまり、拡張した心臓を小さくし、逆流も治さないと根本的な治療とはいえません。それを同時にできるデバイスがあればより効果的だと考え、エモリー時代に研究を始めました。
動物モデルは、豚の心筋梗塞モデルを用いました。心筋梗塞の位置を調整することで、心不全と機能的僧帽弁閉鎖不全症(functional mitral regurgitation; FMR)を再現し、心筋梗塞直後の僧帽弁輪の動きが悪いと数カ月後にFMRを発症しやすいという予測因子を発見しました。この動物モデルで左室の形と弁の構造を同時に治療できる新しいデバイスを開発しており、初期のプロトタイプを使った動物実験で心機能や弁の動きの大幅な改善を確認できました。
このような研究を日本で行うことは難しいでしょう。動物モデルを作成するために、ハイブリッドオペ室で血管造影装置を使いながら、豚の足の付け根からカテーテルを入れて選択的に冠動脈にエタノール注入を行い、どこにどれくらい心筋梗塞を作るか細かく設計する必要があります。このような大動物実験は費用もかかりますし、大動物を取り扱うためには大きな実験施設が必要となります。アメリカにおいても、この規模の実験が行える施設は多くないかもしれません。
もう1つのプロジェクトは先天性心疾患をもった大動物モデルの確立です。先天性心疾患は患者数が少なく、新しい治療法の開発が遅れています。成人の心臓病と違って大型動物を使った実験モデルがほとんどないことも大きな要因になっています。
このプロジェクトはもともと、エモリー時代のラボのボス(医用生体工学が専門)がデバイス開発を専門としていたこともあり、小児心疾患まで研究の領域を拡大したいと考え、オレゴン健康科学大学(Oregon Health & Science University)に在籍する羊の胎児実験専門のPIと共同研究を始めたのがきっかけです。
私たちが着目したのは左室低形成症候群(hypoplasitc left heart syndrome; HLHS)の大動物モデルです。このモデルは1978年に一度トライされましたが、大動物では4日程度しか生存できなかったため、その後40年間くらい誰も取り組んでいませんでした。私のラボも含め、世界中探しても4箇所程度の施設でしか行われていないとても珍しい大動物モデルです。
私のラボで行っている手法は、まだ子宮の中にいる子羊(胎児)の左房の中にバルーンカテーテルを挿入し、左室に流入する血液を制限する方法です。共同研究では、この手法を用いて8日間の血流制限を行いましたが、左室の著名な容量減少と、右室と左室の発育の乖離を認めました。これはニワトリの卵を用いた実験で提唱されていた「血流がなければ心臓も育たない」という”no flow / no grow”仮説を大型哺乳類でも実証した初めての成果です。現在は、より妊娠早期に血流制限を行い、さらにHLHSの心臓形態に近い動物モデルの確立に向けて実験を続けています。将来的にはこの動物モデルを用いて胎児期のうちに介入できる治療法(in utero intervention)の開発を目指したいと考えています。
大動物実験に従事するMD(医師免許持ち)はアメリカでも少なく、多くはPhDのみの研究室主宰者(principal investigator; PI)が臨床で働いているMD(外科医など)に協力を依頼して行っているのが現状です。そのため、手術ができて研究目的も理解し、なおかつまじめに働く日本人外科医が研究チームに加わることはとても歓迎されると思います。
2. キャリア経緯について
もともと手術で人を助けたいとの思いから医師を志し、2002年に長崎大学医学部を卒業しました。当時は、まだスーパーローテートの制度が始まる前だったので、卒業後はすぐ心臓血管外科に入局しました。外科手術を大きく分類すると腫瘍外科と機能再建外科に分かれます。心臓外科を選んだのは、腫瘍外科は完璧な手術をしても再発リスクが避けられない一方、心臓血管外科は手術だけで完結でき、自分が腕を磨けば患者を救える可能性を上げられる点に魅力を感じたからです。
当時の教授が手術の上手な先生だったので、その人のようになりたくて臨床一筋でした。若い頃の私は研究には全く興味がなく、とにかく手術の腕を磨くことに一生懸命でした。大学病院と関連病院で経験を積み、30代になると執刀する機会も増え、最終的には派遣病院の副部長にまで昇進しました。
自分のキャリアについては、外科専門医、心臓血管外科専門医、血管内治療認定医、ステントグラフト実施医などの資格を一通り取り、医学博士も取得して、臨床医として必要な資格が揃った30代半ばくらいから将来像を真剣に考えるようになりました。関連病院で部長職を目指すか、大学に戻って教授職を目指すかの2パターンが見えた時、まだ経験したことのない基礎研究と海外留学に興味がわきました。
概ね順調な臨床医としてのキャリアだったと思いますが、数年間メスを置いてまで海外留学をしてみようと思った1番のきっかけは東日本大震災でした。その当時、被災地から遠く離れた長崎に住んでいましたが、連日テレビで流れる凄惨な映像を目の当たりにし、自分の人生も家族との生活もいつ終わるか分からないと強く感じ、明日死んでも後悔のない人生選択をしたいと思うようになりました。
そこでチャンスがあれば2〜3年の間でも海外で基礎研究をしっかり経験し、基礎研究経験も持った臨床医として、その後は地方の心臓外科医として診療に専念したいと考えました。
医局では学年順に留学する暗黙のルールがありましたが、ちょうど1つ上の学年の先生が留学中だったこともあり、次は自分たちの学年の番だと少し慌てて留学先を探し始めました。その当時、医局の関連施設ではドイツの臨床留学しかなく、基礎研究で行ける場所がなかったので、医局の先輩のつてをたどってエモリー大学心臓胸部外科のラボを紹介してもらいました。それが36〜37歳の時です。
私を受け入れてくれたエモリーのラボは、立ち上げ数年目のまだ小さな研究室で、大動物実験をしたいが心臓外科医のスケジュール調整が大変だと困っていました。心臓手術ができるポスドクが来てくれればありがたいということで、割とスムーズにマッチングすることができました。2015年の夏から渡米しましたが、運良くその2〜3年後にラボのボスが大きなグラントを立て続けに取得し、最終的にはラボメンバー10数人の大型ラボにまで成長しました。
留学当初は「ボスの右腕として、日本だとなかなか経験できない大動物実験を用いたデバイス開発などの研究が続けられれば楽しいかな」と単純に考えていました。しかし留学生活が予定していた3年を過ぎ、もっと長期化する可能性が高くなり、家族と一緒にアメリカで生活していくためには収入をもっと上げる必要が出てきました。ポスドクからResearch Associate、Research Scientistと昇進し、いくらか給料は上がりましたが、まだまだ不十分であったため、大学の研究者を続けながらボスの立ち上げた医療機器スタートアップの社員として雇用してもらう計画を立てました。そのため、副業ができるようにグリーンカード(アメリカ永住権)の申請も開始しました。その計画を進めていた2023年4月、諸事情により突然ボスが大学を去ることになってしまい、ラボ閉鎖の危機が訪れます。そのままラボに残るのかボスの会社に雇用してもらうのか迷いましたが、せっかくならPIを目指して就職活動をしてみようと考えたのです。
その時点で渡米して8年経過しており、ラットなどの小動物の実験を300例以上、ブタを中心とした大動物の実験を450例くらい経験しており、特に大動物を用いた心疾患モデルの確立やデバイス開発について豊富な経験を持っていました。また、アメリカ心臓学会(American Heart Association)が独立してPIになることを希望する研究者をサポートするために提供している中型の研究資金(Career Development Award/3年で3400万円くらい)も獲得していましたし、アメリカ国内の研究者とのネットワークもある程度構築できていました。
そのおかげもあって比較的早く、面接をしてもいいというオファーをもらうことができました。アメリカでの就職活動は、現地まで赴いて自分の研究内容をプレゼンしたり、その施設のキーとなる複数の職員から2日にわたり代わるがわるインタビューを受けたりしなければならないなど、なかなか大変ではありました。この1次面接に合格すると2次面接に招待され、雇用条件の交渉をしたり、また同じようにいろいろな職員からのインタビューを受けたりしました。
3. アメリカでの生活について
妻は高校生の頃にオーストラリア留学経験があったこともあり、海外留学については快く賛同してくれました。子どもたちにも海外生活を経験させたいと思っていたようで、「2〜3年なら」と、渡米準備もいろいろとサポートしてくれました。この夏で10年目になりますが、正直私自身もこんなに長くなるとは思っていませんでした。
留学資金については、渡米前に奨学金もいくつか応募してみましたが、基礎研究の経験が全くなかったこともあり当然受かりませんでした。留学の順番が医局の学年順であったため、自分の学年の番がまわってくるタイミングを考慮して留学生活2年分くらいの貯金は準備したつもりでしたが全く足りませんでした。特に最初の1年は生活のセットアップなどで、あっという間に口座残高が減り、本当にびっくりしました。
アメリカではポスドクとして給料を全額もらっていましたが、ポスドクは家族を養っていける給料を出すポジションではなく、研究者として独立してやっていけるかどうか適性をみるためのポジションです。ポスドクの次のキャリアとして、十分な研究資金を獲得しPIを目指すか、就活をしてインダストリー(企業)に行くか、自分の特性をできるだけ早く見極める必要があります。ずるずるとポスドク生活が続いてしまうとPIになれるチャンスも下がりますし、生活費が高いのでお金もどんどんなくなります。
給料についてはアメリカの多くの研究施設でNIHの規定を参考に設定されています。ポスドクの給料は私が渡米した2015年は4万ドル(約600万円)台でしたが、2025年現在は6万ドル(約900万円)まで上がっています。ただ物価上昇に後追いで調整されているので結局ポスドクとしての生活が苦しいのは変わらず、さらに昨今の円安も加わり、留学生の財布事情はとても厳しくなっています。
アメリカで生活していて1番大変なのは、言語の壁と行政手続きの効率の悪さでしょうか。とくに手続き関係においては苦労が絶えません。電話しても自動音声ばかりでなかなか担当者につながりませんし、つながったらつながったでその担当は自分じゃないと電話を切られたりします。窓口の人の愛想もとにかく悪いですし、書類不備と言われて追い返されたのに実は不備がなかったり、窓口の担当者によってルールがコロコロ変わるなど、とにかく日本では起こらないようなことが多々ありました。
4. 今後の展開について
研究者なのでNIHのR01という大型グラントの獲得を目標にしています。また、現在はテニュアトラックのアシスタントプロフェッサーというポジションなので、契約更新時に予定されているテニュア審査でアソシエイトプロフェッサーへの昇進を目指しています。テニュアトラックとは日本語では終身雇用と呼ばれるもので、研究以外に教育や研究施設でのさまざまな活動に従事する代わりに、研究資金が確保できない期間があっても仕事が保証される雇用形態です。
また現在は、心不全治療用デバイス開発に関連して、医療機器のスタートアップ会社を立ち上げる準備をしています。コロンバスのベンチャーキャピタルやJETRO(日本貿易振興機構)の支援を受けながら、アメリカでの会社の立ち上げ方、どうやったら投資をしてもらえるのかなど実践的な手法を学習しています。
海外留学で成功している人は、もともと日本でも優秀な先生がスタンフォードやハーバードなど有名大学に留学し活躍しているイメージがあると思いますが、意外にそうとは限りません。研究内容の特殊性、所属したラボの当たり外れ、上手にネットワークを拡大できるかどうかなどいろいろな要因が関係してきます。私の場合も順調そうに見えた留学生活でしたが、ラボ閉鎖の危機など予想しないことが突然起きました。成功の秘訣として運の要素も強いと言われがちですが、何が起こっても柔軟に対応できるように常にいろいろと準備しておくことも大切だったなと感じています。
現在は良くも悪くも情報が氾濫しています。情報がありすぎることで「自分には無理、自分には関係のない世界」とブレーキを踏んでしまうことがあると思います。私の時は情報が少なかったおかげで、「失敗したら日本に帰ればいい」くらいの軽い気持ちでチャレンジしました。人から得た情報が自分の状況にぴったり当てはまるとは限りません。情報は参考にする程度にして惑わされすぎず、夢や希望など、やりたいことへ積極的にチャレンジしてみる方が人生は楽しいと思います。