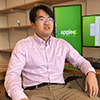2025年から、ミシガン州立大学経済学部でAssistant Professorとして研究に取り組む原湖楠先生。臨床経験を持つ医師として、公衆衛生や医療・環境経済学の観察研究を通じて、制度や政策の改善に貢献したいと考えています。「観察研究で得た知見を、現場に届く形で政策に還元したい」と話すその姿勢の背景には、進路に迷った高校時代や、日本・米国での多様な出会いがありました。越境的なキャリアを歩む原先生に、これまでの道のりと展望を詳しく伺いました。
◆現在の活動について
—2025年からミシガン州立大学経済学部でAssistant Professorに就任されるとのことですが、その経緯について教えてください。
2020年からアメリカ・アリゾナ大学経済学部の博士課程に在籍していました。経済学の博士号を取得した人には、毎年「一斉就活」のような仕組みがあり、大学や研究機関が同時にポストを出し、それに応募していく形で就職活動が進みます。私もその流れに乗って応募した中で、ミシガン州立大学にご縁があり、8月からAssistant Professorとして着任することになりました。
アメリカの教授職のシステムでは多くの場合、まずAssistant Professorとして6年間の審査期間があり、その後にテニュア審査に通ると終身雇用に変わります。そのためまずはこの6年間、Assistant Professorとして取り組んでいく予定です。
—現在はどのようなテーマや分野について研究しているのですか?
私が今注目している、あるいは取り組むことを期待されているのは「エネルギー・環境経済学(以下、環境経済学)」という分野です。アリゾナ大学で指導教官だったAshley Langer先生の講義を受けて面白いと思ったのが興味を持ったきっかけです。一見、医療とは遠い分野に思えるかもしれません。しかし医療経済学と環境経済学には、共通点があるのです。
例えば、医療の世界では、医薬品の品質や価格、治療の安全性などが厳しく管理されています。命に関わることですから、当然の規制です。一方、環境問題も同じです。工場が無制限に汚染物質を排出したり、電力会社が好き勝手に二酸化炭素を排出したりすれば、私たちの健康や地球環境に深刻な影響が出ます。だからこそ、国や自治体による厳しいルールや規制があります。
どちらの分野も、人々の安全と健康を守るために、規制が不可欠なのです。しかし、この規制が常にうまく機能するとは限りません。企業は利潤を最大化するために、法律の抜け穴を探したり、グレーゾーンを攻めたりすることもあります。国が一見して良いルールを作っても、現場で想定通りに動かないことも少なくありません。
そこで私が研究しているのは、このような「規制のある中で利益を最大化する」企業の行動と、それに対する国の政策がどう相互作用するのか、という点です。例えば、再生可能エネルギーが普及する中で、「電力を送る会社」と「再生エネルギーを作る会社」は同じ会社でいいのか、それとも自由に競争させた方が良いのか、といった市場のあり方について分析を進めています。
環境問題は、空気の汚染や水質悪化など、直接的に人々の健康に影響を与えます。このように、環境経済学と医療経済学は、人々の健康に関わるという共通点を持ち、かつ、人々の健康や生活に直接的に関わるからこそ国の規制が厳しく、その中で複雑な経済活動が行われているという点で非常に似ています。そのため医療との近さを感じ、関心を持って研究を進めています。
もう1つ、臨床研究・公衆衛生では、「Heterogeneous Treatment Effect(HTE)」と呼ばれる、治療効果のばらつきに関する研究にも注力しています。同じ治療でも、その効果は個人やグループによって大きく異なります。こうした違いを分析する手法は、計量経済学者も手法の開発に大きく貢献しており、近年では、機械学習を活用して、効果が高い集団を自動的に同定できる技術が発展しています。この手法は、臨床研究でも使われるようになっています。
婦人科腫瘍の治療について、手術か化学療法か、あるいは化学療法の中でどの種類を選択するか決定する際、多くの腫瘍のステージやタイプで指針が確立されていますが、複数の治療法どれでも良いというような集団も存在します。日本のランダム化比較試験では特定の治療法が他の治療法と比べてより有効であるとされたのに、海外ではそれが再現されなかったケースがあります。そこで私たちの研究グループでは、「サブグループごとに効果が異なる」ことが原因の1つではないかと考え、日本のデータから効果のあったサブグループを抽出し、効果の高い集団を同定する試みを進めています。既に日本で成果が出ており、海外データでのさらなる検証を進めています。
最終的には、医師が治療方針を決定する際、どの治療が有効かを推奨することにつなげられるのではないかと期待しています。計量経済学者が手法の発展に寄与していることから分かるように、経済学のバックグラウンドは、手法の理論をより深く理解するのに役立ちます。その知見によって臨床研究にも貢献したいと思い、研究を続けています。
◆これまでのキャリア
—そもそも原先生は、なぜ医師を目指されたのですか?
高校時代は研究者と医師で進路を悩んでいました。父が文化人類学者で、研究職は身近だったのですが、その厳しさも知っていました。一方で、陸上競技をしていたこともあり、スポーツドクターへの憧れもありました。医学部には研究の道もあることを知っていたので、最終的には医学部に入学してから改めて将来の道を考えようと思ったのです。
医学部進学後、スポーツドクターというキャリアについて実際に話を聞くなどしながら検討していました。そんな中、大学5〜6年生の時、公衆衛生分野での第一人者である小林廉毅先生の授業を受けたのです。小林先生の専門の1つは医療経済学で、レクチャーだけでなく研究に触れる機会も設けられていました。もともと研究の道も選択肢の1つとして考えていたので、生命科学系の医学研究室に行ったことはあったのですが、あまり自分には合っていないと感じていたんです。ところが公衆衛生、医療経済学には興味が湧きました。
ただ公衆衛生に進むにしても、最低限の臨床経験は強く勧められているので、初期研修の間は臨床と研究の両方の道を視野に入れ、初期研修を終えてから進路を決めることに。結果的に初期研修修了後は公衆衛生学の博士課程に進み、自分が研究に適しているのか、さらに見極めることにしました。博士課程に進んだからといって、スポーツドクターへの道が閉ざされるわけではありませんし、博士課程修了後に整形外科で後期研修を受けることも十分に可能だったからです。
—公衆衛生学の博士課程では、どのようなテーマで研究されていたのですか?
進学当初は、あまり明確に研究テーマは決まっていませんでしたが、経済寄りの政策評価や、政策や政策変更が患者や医師の行動にどのような影響をもたらすのか、といったことに漠然と関心がありましたね。小林先生の研究室ではレセプトデータを使った研究が盛んに行われていたので、レセプトデータを分析するために、計量経済学も含めて観察研究の手法を中心に勉強していました。
中でも特に時間をかけて取り組んだテーマの1つは「なぜジェネリック医薬品への切り替えが進まないのか」というもの。レセプトデータからどのように薬剤が処方されているのかを分析し、もともと先発薬を処方されていると、それを使い続けたいという「慣性の法則」のような心理が働いているのではないかという仮説を立てました。そして、行動経済学でいう「ナッジ(nudge; 行動を後押しする小さなきっかけ)」によって、どの程度ジェネリック医薬品への切り替えが進む可能性があるのかを分析しました。
もうひとつ大きなテーマとして取り組んだのが、「レセプトデータの正確性」に関する研究です。レセプトデータには医師が入力した病名が記録されていますが、その内容が実際に正しいとは限りません。アメリカなどではこの問題が以前から認識されていましたが、当時の日本ではほとんど検証されていませんでした。
そこでレセプトデータと健診データを組み合わせることによって、高血圧、糖尿病、高脂血症といった生活習慣病がどれくらい正確に反映されているのかを検証しました。
—その後アメリカで経済学の博士課程に進まれたのはなぜですか?
いくつかの転機がありました。1つは博士課程の4年間を経て、公衆衛生分野の研究者としてキャリアを積んでいこうと、ある程度方向性が定まったこと。研究者としてキャリアを積むなら、一度は海外で研究する機会を得た方がいいと、小林先生から強く勧められました。公衆衛生分野でも博士課程を海外で修了する人が増えているのですが、当時の私は「ある程度知識を身につけてから行った方がいいのでは?」と、あまり積極的に海外に行こうとは思っていませんでした。
しかし東京大学経済学部にいらっしゃった市村英彦先生との出会いで考えが変わりました。この出会いが2つ目の転機でしたね。市村先生は計量経済学分野で非常に有名な方です。先生が開催された勉強会に参加し、経済学に進むことが現実的な選択肢となりました。
公衆衛生と経済学には多くの共通点があります。公衆衛生ではランダム化比較試験のような実験が伝統的な手法で、経済では政策のランダム化が難しいため、観察研究を中心に発展してきました。しかし近年、臨床研究・公衆衛生でも、医療レセプトデータなど二次データの観察研究が重視されるようになり、経済学で発展してきた手法を流用できるようになっています。そのため経済学の研究手法に興味が湧きました。すると市村先生から「少なくとも今のところ経済学で強いのはアメリカだから、アメリカで学ぶべきだ」と強く勧められました。
そんな折、市村先生がアリゾナ大学でも教鞭をとることが決まり、同大学博士課程での受け入れが進むことになり、私もアリゾナ大学で経済学の博士課程に進むことに決めたのです。
◆今後の展望とメッセージ
—今後の展望はどのように思い描いていますか?
観察研究を通じて得られた知見を、一歩踏み込んで実際の政策に応用・検証した上で説得的な政策の選択肢として提案していければと考えています。研究成果が実際の政策の議論の俎上に乗ってくるまでは、かなり時間がかかると思います。小林先生も「政策研究で出た成果が実際の政策に反映されるには、10年はかかる」とおっしゃっていたことがありました。実際にはもっとかかるかもしれません。成果が反映されるのはまだまだ先になるかもしれませんが、未来の政策の議論の質を少しでも上げていけるように一歩ずつ質の高い政策研究を積み上げていけたらと考えています。
—最後に、若手医師や医学生にメッセージをお願いします。
臨床にすべての情熱を注げるなら、それはとても素晴らしいことです。ただ、もし少しでも迷いや違和感があるなら、臨床、さらに大きくは医療の世界に縛られる必要はないのではないかと思います。そのような外の選択肢を模索する中で一度海外に出るのは、私にとっては大きな意味がありました。必ずしも欧米でなくても、東南アジアやインドなどでもいいと思います。海外に出て多様な価値観に触れることで「日本で考えていたことが、必ずしも唯一の正解ではない」と気づくことができます。その気づきが、新しい行動や挑戦のきっかけになると思います。
研究の観点でも、日本にも素晴らしい研究者は大勢います。私自身も、日本での経験には大きな価値があったと思っています。ただ私がアメリカに来て驚いたのは、人材の裾野の広さです。たとえばアリゾナ大学のように世界ランキングで東大と同等とは言えないかもしれない大学でも、ものすごく優秀な研究者が大勢いて、とても勉強になりますし、非常に刺激的です。アメリカにはそのような大学が数多くあります。日本に留まっていたら出会えなかった多種多様な優秀な人たちの中で、視野が広がったと思います。その意味でも、一度世界を見てみることは、非常に大きな価値があるのではないでしょうか。
(インタビュー・文/coFFeedoctors編集部)※掲載日:2025年9月9日