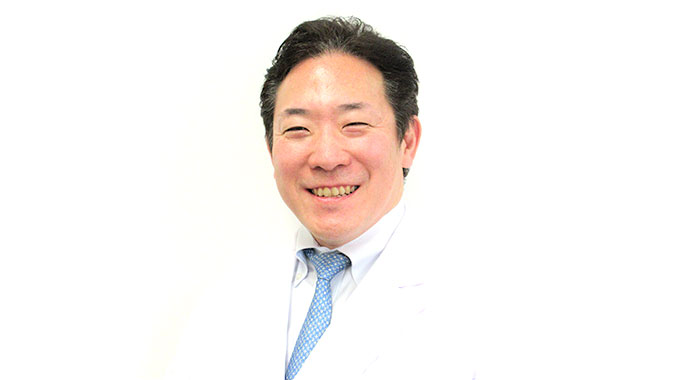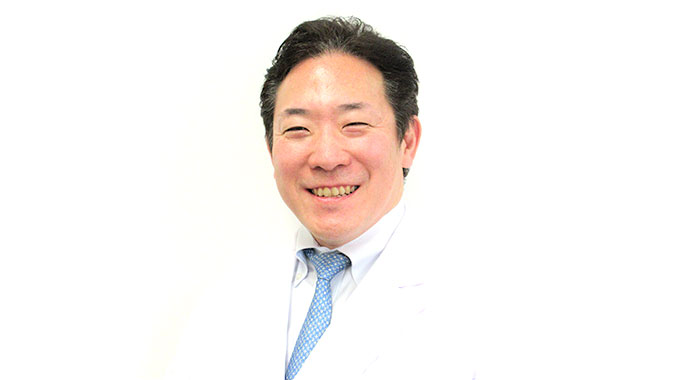限られた人数で手厚いケアを。eICUとの出会い
―留学先のスタンフォード大学では、どのようなことを学ばれているのでしょうか?
2021年6月に新設されたClinical Informatics Managementという修士コースで、最先端の情報技術を活用し、より良い医療の実現を目指す「デジタルヘルス」について学んでいます。内容は多岐に渡り、AIモデリング、シミュレーション、プログラミングコードなどの情報技術、医療現場での新規技術マネジメントやファイナンスに及びます。極めて実践的で、例えばファイナンスでは医療機関でAIを活用するのに必要な費用や、その資金をどのように調達し運用するかまで学びます。ビジネス、情報技術、医療が三位一体となったカリキュラムは、今後「働き方改革」が進む日本の医療において、非常に役立つ知識だと感じています。
―スタンフォード大学への留学のきっかけを教えてください。
eICUとの出会いが大きいですね。私は2013年から昭和大学医学部の麻酔科学講座で教授を務め、2016年に大学病院の副院長に就任しました。病院の中枢としてさまざまな課題を考える中で、アメリカで開発されたeICUという最先端技術があることを知り、ぜひ取り入れたいと考えたのです。
というのも、昭和大学にはICUと手術室を備える大型病院が東京、横浜に各2院あります。専属医師による24時間体制のICU運営には、集中治療医が10名必要です。しかし、当時、ICU加算を取っている病院は全国で約700あるのに対し、集中治療専門医は国内に1800名程度。単純計算で4つの病院に10名ずつ集中治療専門医を配置し、昭和大学で計40名確保するのは、現実的ではありませんでした。
そこで生産性を向上できるツールは何かないかと探している時に、eICUに出会い、デジタルテクノロジーを使えば、限られた人員で手厚いケアができると考えたのです。そこから多くの方の尽力があり、決して安価なものではありませんが、導入が叶いました。
eICUを使って、まず東京にある2院をつなぎ、病院内では重症対応機能を持っている部門、ICUとCCU、救命救急センターの合わせて5つのユニットを連携させ、全てをサポートセンターで一元的に支援できる体制を整えたのです。現在もそのシステムは使われており、ハイケア病棟の重症患者の方などにも、モバイルユニットを使ったサポートの手を広げています。
―eICUの活用の幅は、当初の目的以上に広がっているのですね。
実は、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の治療にも役立っています。新型コロナの流行下では、感染防止のために、同じ病棟内でも各病室が隔離病棟のような形にならざるを得ません。そのような中でeICUの双方向カメラやモニターを使うことで、新型コロナ感染者を直接治療する医療者の人数を最小限に限定することができています。そして、その方達を遠隔でバックアップする体制を整えたのです。
導入時には予想していなかった使い方ですが、そういった経験から、さらに医療に役立つデジタルテクノロジーがあるのではと考え始め、シリコンバレーを擁し、AIなど最先端の情報技術が豊富なアメリカへの留学を決めました。
AI機器を有効活用できるフレームワーク化を
―改めて「デジタルヘルス」の必要性について、先生の考えを教えていただけますか?
今後、働き方改革や円安が進む中で、人、時間、お金のリソースはますます限られてくるので、医療者の数を増やすのではなく、手間を軽減しながら、より生産性の高い医療を提供する必要があります。そこで「デジタルヘルス」の力が重要となるのです。
生産性向上のために大切なことは、AI機器そのものよりも、実装モデルとフレームワーク化です。いくら優秀なAI機器を作ったとしても「人間が何を入力して、何を結果として導き出し、どう使っていきたいのか」というフレームワークがきちんと設計されていなければ、AIの機能をうまく使いこなせません。AIが導いた答えは臨床現場で、医師や看護師に使ってもらい、患者さんへ何らかの形でリターンしなければ費用をかけて導入する意味がないのです。
―生産性向上のために課題となっているのは、どのような点でしょうか?
デザインは大きな課題だと思います。医療は高齢者に最も身近なものですから、その方達も使えるデザインが必要です。例えば電車の改札機でICカードをタッチするシステムは、幅広い年代の方が当たり前に使っています。そのくらいユニバーサルなインターフェイスを用意し、誰もが使いやすいデザインにする必要がありますが、残念ながら「デジタルヘルス」はまだその域には至っていません。もう少しコモディティ化する必要性を感じています。
その要因の1つには、オープンリソースではなく、各ベンダーが独自設計で顧客を囲う傾向があることが挙げられます。Windowsが搭載されたPCの場合、NECから富士通に代えたとしてもすぐに使えますが、電子カルテや血圧計はそうはいきません。仕様が異なるためベンダーを変更すると、まず使い方を覚えるのが大変です。医療と他の領域を比べると、明らかにその点が違います。
これは日本に限った話ではなく、世界各国で共通の問題です。自動車のアクセルとブレーキの位置のように、ある程度揃えてもいいのではないでしょうか。すぐには難しいとは思いますが、そこをもう少しオープンにできれば、世界中で大きな利益が享受できるのではないかと考えています。
―その他に、先生が課題と感じている点はありますか?
医療の本質に関わる点ですが、一対一のケアを見直す必要があると考えています。世界でこれだけ人口が増えていますが、医療者はあまり増えていません。すると現在の一対一のケアのままでは、いずれ立ち行かなくなります。ですから、変える必要に迫られているのです。
では一体どこを変えるのか。病棟や在宅ケアの人員配置にメリハリをつけたり、医療関連の資格を持たない方が補助できる範囲を広げたりするのも1つの方法かもしれません。また重症化する前に発見し、早期治療につなげる仕組みを作ることも有効だと思います。手術や急変対応など人員が必要なところは一対一に、それ以外の部分はeICUや民間企業の手も借りながら、早期発見、治療、ケアというサイクルをスムーズに回し、全ての場面で生産性の向上を考えていく必要性があると感じています。
どこまでの医療を一人で行うのか、その線引きは命に係わるため、非常に難しいものがあります。ですが、大切なのはまず一歩進んで、そこから見直していくことではないでしょうか。リスクばかりに目を向けて進まないのではなく、前身しながらリスクを減らしていく。そうしなければ、財務的にも人員的にも医療体制がいずれ破綻し、全員が不利益を被ることになってしまいます。そしてこれは、医療業界だけに留まらず、国家経済、社会福祉にも直結してくる大きな課題です。
医師人生は45年。限界を決めずに挑戦を
―最後に、これからキャリアを積んでいく若手医師に向けてアドバイスをお願いします。
昨今、専門医を育成するためのさまざまな制度が整備されていることは非常に良いことだと考えています。ですが、そこにとらわれ過ぎている方が多く、もう少し自由にキャリアを考えてもいいのではないかとも思います。先ほどもお話しましたが、医療の問題を解決するためには経済や為替、薬価について考えることなども必要です。凝り固まらず、広い視点を持つことが重要です。ですから若いうちは、まずは自分が好きなことに取り組んでもいいのではないでしょうか。
ライフイベントを制限しないことも重要です。学生や研修医から「専門医を取ってから子どもを産んだほうがいいでしょうか」と質問された時には「結婚や出産は貴重な巡り合わせだから、まずはライフイベントを大事に」と答えています。
人生は一度きり。だからこそ、自分の人生を生きることを大切にしてほしいのです。もちろん専門医や資格を持っていることで社会貢献はできますが、それはあくまで人生を彩るツールの1つです。もっと大切なのは、一人ひとりがオリジナルな人生を生きること。70歳で引退すると仮定すると、免許取得から45年間、医師としての人生は続いていきます。出産や子育てに労力が割かれる15~20年ぐらいの間、適切なライフワークバランスを取りながらでもキャリアを前に進められる多様性を認める社会の構築は重要です。専門医の取得はだいたい最初の10年の話ですから、そこを目標にするのではなく、長い医師人生を想像しながら、人生の選択をしてほしいと思います。
―起業される医師も増えていますよね。
教室の若手医師から起業の相談を受けたことがあります。「あとのことを気にせず、どんどんやれ」と背中を押しました。医師として現場に帰りたくなったらいつでも帰って来れるように周りが支援すればいいんです。週に一日でも臨床医を続けながら、自分の取り組みたいことにチャレンジしたらいい。医師か起業か、二者択一ではなく、挑戦したいこと全てにチャレンジすればいいと思います。自分を縛り、可能性を閉じてしまっているのは、自分自身なのではないでしょうか。
人生、回り道がプラスになることもあります。私は卒後入局した帝京大学医学部附属市原病院で、恩師である森田茂穂先生に、突然、医師3年目でオーストラリアの病院に臨床医として派遣されました。その後MBAの取得、経営企画、医療安全などの業務も指示され、無我夢中でこなしてきました。
その時は「なぜ自分が?」と疑問を持っていましたが、病院の副院長になった際、全ての経験が不可欠だったと分かりました。経営も医療安全も私だけなら「専門領域ではない」と自分で限定していましたが、森田先生は将来必要になると見通されていたんですね。医療は複雑な事象が絡み合う科学ですから、何が役に立つかは誰にも分かりません。「〇〇科医だから」とためらわず、欲張りになって、どんどん挑戦していってください。それが自分でも思わぬ形で、明日の医療に役立つ日が来るかもしれません。
(インタビュー・文/coFFee doctors編集部)※掲載日:2022年6月14日