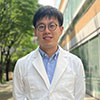医師12年目の安藤崇之先生は、総合診療医として慶應義塾大学医学部総合診療教育センターに属し教育や研究に従事しながら、株式会社PIERを創業して代表取締役社長を務めています。後期研修では初の病院研修での家庭医療専門医取得、母校では総合診療科の立ち上げに携わるなど、新たな道を切り開いてきました。プライマリ・ケアの質の向上、全ての人のウェルビーイングへの貢献に取り組みたいという思いを一貫して持ち続けてきた安藤先生に、キャリア選択への考え方や、展望について伺いました。
◆民間病院と医局、双方のメリットに
—現在、取り組んでいることを教えてください。
慶應義塾大学医学部総合診療教育センター助教として教育や研究に携わる一方、株式会社PIERを立ち上げ、代表取締役社長としても取り組みを進めています。
同社では、主に2つの事業を展開しています。1つ目は、地域の病院に向けたコンサルティング。たとえば人手不足に悩む地域病院は、総合診療医を1名配置することで解決できる場合も多いのですが、総合診療医の確保にも苦労しています。そこで私たちが、さまざまな企画を立て人材を集める支援などを行なっています。2つ目は研究支援です。民間病院に所属する若手医師に対して、論文執筆に至るまでの研究支援をしていて、これまでに亀田ファミリークリニック館山でリサーチの支援をしました。
地域の病院は人材確保や研究ができるようになることで活性化しますし、それが病院の研修プログラムの付加価値にもなります。そして大学側は、知識やノウハウを提供することの対価として資金を得る。全員にとってメリットがある上に、お金がしっかり循環することを意識して事業に取り組んでいます。
—どのような背景から株式会社PIERを創業されたのですか?
大学では、各医局が秘書の人件費や備品の購入費などの資金を自分たちで工面しなければいけません。ある程度研究の実績があると国などから研究費をとることができますが、それも学会への出張費や論文の出版費用などに充てるとすぐになくなってしまいます。しかし大学には知識やスキルをもった人が集まります。一方、地域の病院には臨床データや臨床現場の課題があるにもかかわらず、指導者やノウハウが不足しているため、研究活動が行き詰まるという現状がありました。
そこで、大学が持つ知識や能力を、専門的な知識やスキルを必要としている地域医療の現場に提供し、大学の医局はその対価を得ることで研究や医局運営に必要な資金を得ることができるのではないかと考えたんです。
そのアイデアを、中学・高校時代からの同級生であり、現在のビジネスパートナーでもある石川翔太さんに相談したところ、彼も賛同してくれ、共に会社を立ち上げることになりました。彼は医療関係者ではなく、地方スタートアップ支援やコンサルティングの分野で活躍しています。起業や経営、コンサルティングの知識も学べることは、総合診療科の付加価値にもつながると考えました。医療業界とは異なるビジネス領域のノウハウを取り入れることには「今までとは異なる、次世代の医局を創る」というメッセージを発信したいという思いも込められています。
今後、株式会社PIERの事業をどのように展開していくか、そして医局に新たに加わる方々とどのように関わりながら価値を生み出していくかは目下の課題ですね。
◆当時の大学に総合診療科はなかった
—家庭医療を専門に選んだきっかけを教えてください。
大学3年生の時のイギリス留学がきっかけです。そこでGeneral Practitioner(GP)に出会い、これこそ自分が目指したい医師の姿だと感じました。しかし当時、在学していた慶應義塾大学には総合診療科がなく、周囲からはほとんど理解されませんでした。そこで私は、家庭医療を学ぶためにアメリカへの臨床留学を視野に入れるようになったんです。そして大学卒業後は、家庭医療を学べる環境や理念に共感し、亀田総合病院で初期研修を受けることにしました。
—アメリカへの臨床留学は実現されましたか?
米国の医師免許であるECFMGを取得し、着々と準備を進めてはいましたが、医師3年目に再度アメリカに短期留学をしたときに考えが変わったんです。アメリカの教育システムは素晴らしい部分がありますが、誰もが最低限の医療を行えるようになるための仕組みであり、ある程度の臨床経験を積んできた今の私にとって、必要ではないと感じるようになって——。
また、プライマリ・ケアは国の医療制度の影響を大きく受けるため、アメリカで専門医を取得しても日本ですぐに活用できないことも。そのためまずは日本で専門医を取得し、また本当に必要だと感じたタイミングで留学を検討することにしました。
—亀田総合病院でどのようなことを学びましたか?
亀田総合病院で初期研修を修了し、安房地域医療センターという150床の関連病院で後期研修を行い家庭医療専門医を取得しました。病院を基盤として研鑽を積み家庭医療専門医を取得したケースは初めてのことでした。安房地域医療センターは比較的小規模な病院だったので、時にはスタッフ人員不足などもあり後期研修2年目から主治医のような役割を担うようになり、3年目にはチーフレジデントの制度を新たにつくりました。このときの経験は、私にとって大きな成長の糧になっています。また、病院と診療所での勤務をすることで、家庭医療は勤務場所が違っても本質的には同じだと実感できたことは、とてもいい経験でしたね。
—後期研修修了後、すぐに慶應義塾大学に移っています。どのような経緯だったのですか?
大学での仕事を始めるきっかけは、母校の先生からの電話でした。「慶應義塾大学に総合診療科が新設されて、学生教育がスタートするため、教えられる人材を探している」とお誘いいただいたんです。それまで大学とは特に連絡は取っていなかったのですが、学生時代にも一貫して家庭医療への思いを語っていたことを覚えていてくださり、このオファーにつながったのだと思います。
実は学生時代、海外で家庭医療の専門医を取得して、日本でモデルとなるプログラムを構築し、そしていずれは母校で家庭医療の講座を……との将来を描いていました。思いがけず後期研修を終えたタイミングで卒前教育に携わる機会が訪れたことは、時代のニーズの変化を肌で感じた瞬間でもありましたね。
学生全員が一度は総合診療に触れて選択肢の1つとして考える機会をつくることは、これから家庭医を増やしていく上で必要不可欠だと考えました。また大学での仕事は簡単なことではないだろうと想像していましたが、母校という環境に加え、学生時代にお世話になった先生方からのサポートや、前職で自ら道を切り開いてきた経験も大きな後押しとなり、引き受けることを決めました。
―慶應義塾大学ではどのような取り組みをされてきたのですか?
2019年4月に着任し、最初の8カ月間は臨床実習のカリキュラム作成に取り組みました。これまで総合診療科の実習は、6年生で選択した生徒が年1〜2名程度しか受けていなかったのですが、2020年1月から5年生全員が2週間の実習を受けることになり、毎週6名ほどの生徒を受け入れることになったからです。
「必ず学生全員が家庭医と接する機会をつくる」というコンセプトのもと、大学内外の協力を得て準備を進めてきました。慶應義塾大学病院の総合診療科は外来診療しか行なっていないので、全員を指導するためには院外のリソースを探す必要がありました。東京近郊で勤務している家庭医を紹介していただき、30近くの施設へ協力をお願いした結果、生徒全員が家庭医療専門医が在籍する施設で臨床ができるカリキュラムが出来上がりました。
―大学で総合診療科を設立し、成果は感じていますか?
実習を通じて総合診療科に興味を持つ学生は着実に増えています。そのため総合診療ゼミを立ち上げ、月1回オンラインで勉強会を開催するほどに。現在、カリキュラム変更初年度に教えた学生たちが専門を決めるタイミングとなり、総合診療科を選択する人も現れ始めました。今年度は同大学に1名、亀田総合病院に2名が入職。専門志向が強い同大学において、総合診療科というキャリアを選ぶ学生が出てきたことは、大きな成果だと感じています。
着任したばかりの頃は、この大学の総合診療科の存在をほとんど知られていませんでした。
そのため薬剤師や退院支援部門、災害対策チームなど、多職種の方々と連携する取り組みを進めてきました。また研究活動においても日本プライマリ・ケア連合学会で日野原賞を受賞するなど、実績を積み重ねてきました。このように学内外での活動を通して地道にアピールを続けることで、徐々に評価を得てきていると感じています。
◆軸を持つことでその時最善の選択ができる
—どのようにしてビジョンの軸を持ち、キャリアを形成されてきたのでしょうか?
中高生の頃に「自分は何のために生きているんだろう?」と自問自答する中で、人生の意味は自分でつくるしかない、自分が生きていてよかったと思ってくれる人を最大限に増やそうと考えるようになり、その方法が私にとっては医療でした。
最初は、より多くの人を救うためには目の前の患者さんを救う臨床が重要だと考えていました。しかし大学2年生のある授業で「臨床だけでは診療できる人数に限りがある。しかし研究は未来の数千人、数万人を救える可能性がある」という話を聞き、ハッとしたんです。医療システムも研究と同じで、システムを変えれば自分が直接接していなくても救われる人がいます。単純に家庭医療が好きということもありますが、それ以上に、社会に必要とされていて、取り組むことで世の中が良くなるという確信が、総合診療科の道を進む大きな原動力となりました。
理想のキャリアプランを思い描いても、現実はその通り進むわけではありません。それでも、日本のプライマリ・ケアの質の向上、そして全ての人の健康とウェルビーイングに貢献したいという根底にある思いが揺らぐことはありませんでした。自分のビジョンがはっきりしていれば、想定外のことが起きても、目の前に現れる選択肢から自分にとって一番いい選択ができます。その時々で、どうすることが周りの組織にとって最も大きなインパクトを与えるのか、自分の価値を最大化できるのかを考えて行動に移すこと。それを大事にしています。
—今後、どのようなことに取り組んでいこうと思っていますか?
プライマリ・ケアの質の向上のために、まずは家庭医療専門医を増やしていきたいと考えています。そのためには教育だけでなく、制度設計、総合診療が実際にどれだけの効果を生むのかという検証や研究にも注力する必要があるでしょう。そして最終的には政策にも関与していくことを目指しています。
現在の職場は研究や教育にも従事でき、医療政策に関わっている先生方もたくさんいて、とても良い環境です。しかし、より自分の目指すところへ近づけるチャンスがあるのであれば、今の職場や地位にしがみつくことがないようにしたいですね。そのためにも、この職場で築き上げてきたものが、私が離れてもなくならないように属人性を排除しながらつくり上げることは意識しています。
—後進へのアドバイスをお願いします。
医師人生は長く、専門医取得後も30年、40年は働くことになるでしょう。その長い医師人生をかけて取り組みたいことや、医師を引退した後にどのような世界にしたいかという視点を持ち、キャリアを選択するといいのではないでしょうか。
時代の変化はとても早く、私の想像していたよりも10年も20年も早く変化しています。だからこそ将来の目標をしっかりと持っていないと、時代に振り回されてしまうかもしれません。成し遂げたい目標を持ち、そこに近づけるのであれば、とりあえず時代の波に乗ってみるといいのではないでしょうか。また、迷いが生じた時には1日以上悩まないことをおすすめします。大抵の場合、心の中では答えが決まっていることが多く、悩んでいる時間はもったいないと思うからです。
(インタビュー・文/coFFeedoctors編集部)※掲載日:2025年3月11日