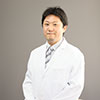「緩和ケアポケットマニュアル」の著者であり、2023年から湘南鎌倉総合病院総合診療科部長を務める宇井睦人先生。総合診療医として臨床現場で活躍しつつ、緩和医療をより多くの医師が学べる場づくりも行っています。その背景にある問題意識や「総合診療と緩和医療の二刀流」のキャリアを選んだわけを伺いました。
◆全ての医師が実践的な緩和医療を学べるように
―現在、どのような活動をされているのか教えていただけますか?
私の専門は総合診療と緩和医療です。2013年頃から二刀流で働いていますが、実は全人的・総合的に患者さんや家族を診るという意味で、両者はとても相性の良い領域なのです。2022年に湘南鎌倉総合病院総合診療科に籍を移し、2023年4月から同科の部長を務めています。院内の緩和医療に関する相談は主に総合診療科で受けており、 教育も兼ねて自分の不在日も総合診療科のドクターに対応してもらって、適宜、遠隔でも指導しています。
他にも2023年4月から「緩トレ」という緩和医療の基礎体力をつけるトレーニングプログラムを定期的に開催しています。大体2週間に1回、1時間のペースでオンライン勉強会を開き、YouTubeにアーカイブ動画を溜めています。
―「緩トレ」について、もう少し詳しく教えてください。
レクチャーを行うこともありますが、私の著書「緩和ケアポケットマニュアル」(南山堂)などを参照しつつ、臨床現場でどのように応用するかについてディスカッションを行っています。
現場で「こういう薬を使いたい」と思った時、パッと参考にできる資料を持っていることが重要だと考えています。そして、その内容をすぐに使えることも。そのため「緩トレ」では「緩和ケアポケットマニュアル」を読み込む機会をつくりつつ、実際の患者さんにどう使用するかまで考えてもらい、より質の高い緩和医療を提供してもらえたら――そんな思いで始めました。
―その背景にはどのような課題感があるのですか?
まず緩和医療を学ぼうと思っても、体系的に学べる機会が少ないのが現状です。なぜなら緩和ケア医が不在だったり、いても非がん疾患には対応しないなどの理由で、各科の医師が自己流で行わざるをえない環境の医療機関が非常に多いからです。
そして、基本的な緩和ケアは全ての医療者が提供できなければいけないと言われていますが、残念ながら現状はそうはなっていません。特にこれからますます患者数が増える在宅医療での領域に、医療用麻薬をはじめとした緩和医療を提供できる医師が少なく、在宅看取り率の低迷につながっています。この点には強い問題意識を持っています。
また、超高齢社会で手術など侵襲的な治療ができない患者さんが増えるのに比例して、「医療の無力さ」を感じる瞬間も増えていると思います。実際、私自身も「自分はなんて無力なんだ」と思ったことが何度もありました。とりわけ感受性が豊かな専攻医は、患者さんに何もできないと感じる自分に無力さを感じ、結果ドロップアウトしてしまうこともあるかもしれません。
しかし緩和医療を学べば、「医師として患者さんに提供すべき医療はできている」という自信がつきます。特に若い医師が緩和医療をしっかり学べば、患者さんやご家族のためだけでなく、プロフェッショナリズムを感じながら医療職を続けられる一助になると思うのです。
もちろん、誰もが緩和医療専門医ほどの知識を身につける必要はないでしょう。ただこれからの日本社会構造や医療のあり方を考えると、全ての医師が緩和医療のスキルを学べる場をつくる必要があるのではないか。そう考え、全国どこからでも緩和医療を学べるよう、onlineトレーニングとして「緩トレ」を始めたのです。
◆娘の生涯から「緩和医療にも軸足を置こう」
―宇井先生はなぜ、総合診療と緩和医療の二刀流というキャリアを歩まれているのですか?
私は千葉県の九十九里浜に面する海や緑の多い地域で生まれ育ち、いわゆる「赤ひげ先生」をイメージして医学部に入学しました。そのため、当初から今で言う総合診療を志望し、多少は別の進路に気持ちが揺れ動くこともありましたが、最終的にはその志に立ち返って総合診療医になりました。
緩和医療に関しては、純粋に苦手だったので学びたいと思ったことが最初のきっかけです。日本の総合診療科ではあまり抗がん剤投与をしていないこともあり、夜間当直の際、化学療法中の患者さんが運ばれてきた時などの対応に、全く自信を持てませんでした。しかし、日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人はがんで亡くなります。がん患者さんを診ずに総合診療医として過ごすほうが難しいですし、ジェネラリストを名乗っておきながらがんが診られないのは、総合診療医として不十分だと考えたのです。
そんな時に長女が生まれましたが、18トリソミーという平均寿命が約1年しかない染色体疾患があり、1年3カ月で亡くなりました。娘の短い一生を通して、人の“生き死に”の意味や終末期のプロセスの価値、ひいては安楽死の議論まで、本当にさまざまなことを考えました。
例えば、娘のような医療的ケア児に多額の資源を投入すべきではないという意見を持っている方もいますが、一般的に医療や看護はそのような人も助けています。その考えがなければ、障がいがある方や病気でこれから亡くなるであろう方を見捨てるような優生思想的な社会になってしまうのではないか。そのような資源投入や緩和ケアに価値を置かない社会には、もしかしたら幸福な未来はないのかもしれない――もちろんその反論や別の角度からの見方についても、何度も何度も自分の頭で考えました。
このように生死について深く考えた経験は習慣となり、緩和ケアを必要とする患者さんやご家族の気持ちを理解する大きな助けになっています。自分の適性も緩和医療・緩和ケアにあるのではと考えられるようになり、親和性の高い総合診療との二刀流で、臨床や教育を続けています。

◆緩和医療に携わるからにはアートを学ぶことは宿命
―現在、アート(芸術)も学ばれていると伺いました。
カナダの有名な医学者であり医学教育の基礎を築いたウィリアム・オスラー先生は、100年以上も前に「医学は不確実性のサイエンスであり、確率のアートである」という格言を残されています。それほどまでに医療の現場は科学だけで通用するものでもなく、アートの部分、つまりケアや優しさ、感性といったものだけでも完結できる世界ではないと私は解釈しています。
翻って今の臨床現場を見ると、科学的なエビデンス優位でアートの要素が重視されておらず、むしろ枯渇しています。患者さんが抗がん剤治療を中止する一番の理由は「医師とのコミュニケーションがうまくいかないから」というアンケート結果が出ていたり、患者さんにも医療スタッフにも前時代的な高圧的態度で接する医師がいたり――アートを軽視しサイエンス偏重の医療が浸透してしまっていると言えると思います。
また緩和医療には、より一層アートの要素が必要です。とりわけ生命の意味や価値など繊細で倫理的な質問を受ける医療現場では、緩和ケア医でなくとも患者さんの気持ちを慮りつつ、深い思索と見識を基盤とした誠実な対応が求められます。
そういった問題意識から、医療や介護にももっともっとアートの要素が必要だろう、と感じていました。そんな時、『太陽の塔』で有名な岡本太郎さんの「絶望を彩ること、それが芸術だ!」という言葉に、雷に打たれたような衝撃を受けました。「私が携わっている緩和医療はまさに、患者さんの底なしの絶望をわずかながらでも彩るものなのではないか」と。
このような経緯から「私が緩和医療に携わるからにはアートを学ぶことは宿命ではないか」と考え、2023年度から芸術系の大学院に入学しました。すでに診療では芸術を学んでいる効果が出始めていると感じていますし、いずれ医療者教育にも落とし込んでいければと思っています。
―最後にキャリアに悩んでいる読者へメッセージをお願いします。
先輩や同僚にキャリアの相談をすることがあると思いますが、あなたにピッタリ合うキャリアを提示してくれる人はおそらくいない、という点を強調したいですね。相談に乗ってくれる方は誰でも、自分の経験やキャリアに基づいてしか語れないものだからです。もちろんロールモデルの一人になる場合はありますが、自分のキャリアは自分自身でデザインしていかなければならない。その意識をしっかり持っておくことが大切だと思います。
自分であれこれ考えながら主体的にキャリアを築いていくのは楽しいものです。不確実性の高い時代ですが、選択できる自由があることをぜひ前向きに捉えながら、自分だけのオリジナルなキャリアをデザインしていってほしいですね。
(インタビュー・文/coFFeedoctors編集部)※掲載日:2024年1月23日