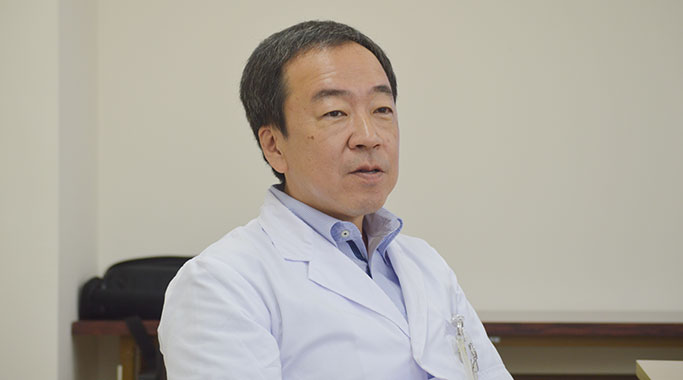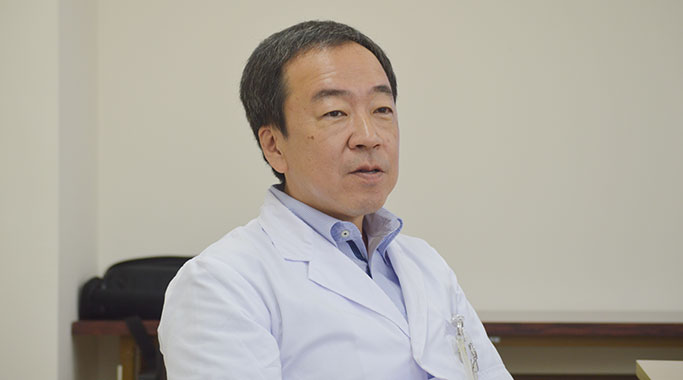途上国を見て、地域の重要性を知る
―これまでのキャリアを教えていただけますか?
高校生の時にマハトマ・ガンジーのドキュメンタリー映画を観たことや、マザーテレサが来日して講演されていたことをきっかけに、将来は開発途上国の医療支援をしたいと思うようになり、医師を目指しました。
精神科医として旭中央病院に勤めるようになってからも、ずっとその機会がないかと探っていました。ただ、精神科で一番大事なのが言葉と文化なので、外国人として精神科の医療支援に入ることは非常に難しいのではないかとも思っていました。
そのように考えていたのですが、医師13年目の時に、カンボジアに駐在して精神科のボランティアをされている方と出会い、1週間カンボジアへ研修に行きました。カンボジアは1970年代のポル・ポト政権下で医療が崩壊、その後立て直しに入っているものの、非常に厳しい状況にありました。当時、精神病床が国内に10~16床。カンボジアの人口が1200万人なので、100万人に1床です。その状況にも驚きましたが、病床がない分、ボランティアベースで訪問サービスや通所リハビリのサービスを稼働させようとしていたんですね。一方、先進国である日本の精神医療は病院中心のまま-。カンボジア見学を通して、地域でのサービスを充実させることの重要性に気付かされたのです。
―その経験から、「旭モデル」と呼ばれる地域型精神医療モデルの構築を始めたのですか?
そうですね。そこから、精神医療先進国と言われている、カナダ・バンクーバーやイタリア・トリエステの研修にも行かせてもらいました。とりわけバンクーバーが衝撃的でした。バンクーバーでは約50年かけて、大規模精神科病院に最大5500床あったところから約180床にまでダウンサイジングしていました。その最終段階の時期に研修させてもらったのです。入院施設も充実しているのですが、病院ではなく地域にシフトしている―。それが非常に衝撃的でした。
もともとバンクーバーの精神医療の話は、大学入学時から知っていました。しかし、見ると聞くとでは大違い。実際に研修に行ってみたら、実感としては半世紀以上違う気がしました。
一方のトリエステは、人口20万人に対して総合病院精神科が1施設のみ、病床はなんと5床だけでした。5床しかないので、忙しく患者さんの受け入れ、退院を繰り返しているのかと思いきや、患者さんは1名だけ。精神疾患があっても地域で暮らしているのです。本当の意味での地域型精神医療を実現できたら、日本でもダウンサイジングして、地域に患者さんを帰していけるのだと確信しました。
「旭モデル」精神科患者さんを地域へ帰す
―実際に「旭モデル」はどのように構築していったのですか?
2002年から、多職種による精神科サービスをリフォームするためのプロジェクトを始めていきました。その中で、救急から治療、リハビリ、退院支援、地域生活支援までの一貫したサービス提供体制を確立して、サービスの多くの段階で精神科医、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士、薬剤師などの多職種チームを編成しました。
翌年には長期在院調査を行い、入院患者233名のうち、1年以上の長期在院患者が全体の65.2%を占めていることが分かりました。スタッフとディスカッションを重ね、長期在院患者の半数は要入院継続として、翌年から残りの半数を退院させていくプログラムを始動しました。
残念ながら長期入院の患者さんの一部は、近隣の医療施設へ転院する結果になりましたが、患者数の減少に合わせて病床数をダウンサイジングしていき、2004年から13年かけて、237床から40床にまで削減しました。
-退院した患者さんに対する地域でのサポートはどのような形で進めていったのですか?
2009年に精神科訪問看護ステーション「旭こころとくらしのケアセンター」を、2012年には「コミュニティメンタルヘルスチーム(CMHT)」を発足させ、訪問支援を充実させていきました。CMHTのチームは専従の看護師、精神保健福祉士、作業療法士の6名と、非専従の精神科医3名で構成しています。患者さんの地域定着、入院・再入院防止のための生活支援をコーディネートするために、入院時から患者さんの退院支援に介入してもらっています。また、グループホームをはじめとするその他の社会資源との連携も担ってもらっています。
他にも、2010年に移行型グループホーム「ぴあハウス」の開設や、その他のグループホームの開設を支援。さらに2014年からは2カ月に1回、保健所が中心となって、地域内の4精神科病院、1クリニックの精神保健福祉士が地域連携会議を開催しています。そして、重症患者さんでも地域生活を継続できるよう、保健所と月に1回ミーティングを実施。保健所が入ってくれることで、緊急時に警察も動いてくれることが多く、地域連携が強化できるためです。
このような連携体制を構築できたことで、平均在院日数が50日を下回るようにもなり、救急受診者数はピーク時には年間1,440件だったのが2014年度には569件にまで減少しています。
ここまで進めてこられたのは、「全ては患者さんのために」「精神科なくして総合病院と称されない」という当院の理念や、その理念のもと長年貢献してくれている人材がいること、千葉大学大学院精神医学教室のご支援、地域の精神保健医療機関、「ロザリオの聖母会」や「はんどいんはんど東総」といった地域の福祉団体やボランティア団代のご協力など、「地域型精神医療」を進めるための文化的素地が整っていたことが大きく影響していると思います。
日本だけでなく開発途上国の精神医療にも貢献する
―青木先生の今後の目標を教えていただけますか?
もちろん国内の精神医療も、まだまだ改善の余地があります。患者中心の医療が行われているかというと、必ずしもそうではなく、地域に患者さんを帰していくこともさらにできると思います。しかし国内のことばかりではなく、カンボジアなど開発途上国にも目を向けなければいけないと考えています。
私は「旭モデル」の構築がひと段落した昨年から、クラウドファンディングで精神医療サービスをより多くの人へ届けるための往診車購入資金を集めるなど、本格的にカンボジアの精神科支援にも力を入れ始めました。
カンボジアは先程も言った通り、医療制度立て直しの途上です。病院の精神科外来では、一人の医師が1日100名を超える患者さんを診ています。また、郡立病院から歩いて徒歩10分のところにある家の庭にはケージが置かれ、15歳の男の子が縛られて入っていました。その横で、お母さんが「5年前からケージの中に入れているが、面倒を見るのが本当に大変」と涙ながらに訴えていました。人口の0.5%、つまり200人に1人くらいは私宅監置されているというデータを見たことはありましたが、実際に目の当たりにすると、言葉になりません。
内戦や災害などを経験したカンボジアには、心の病を負っている人が想像以上にたくさんいます。メンタルヘルスギャップといって、先進国よりはるかに開発途上国の人たちのほうが、メンタルヘルスを崩しているのです。このギャップを少しでも埋められるように、今後はカンボジア、さらには他の開発途上国の精神医療にも貢献していきたいと思っています。