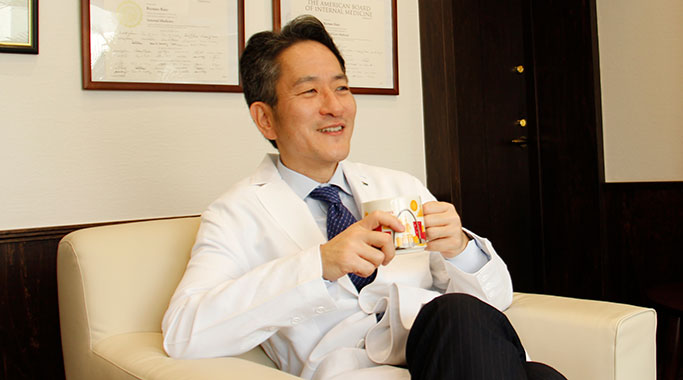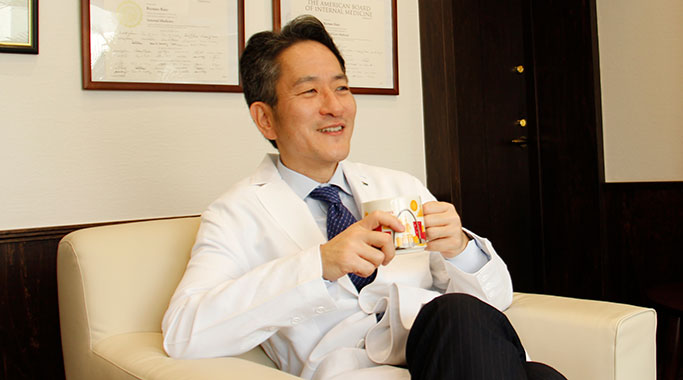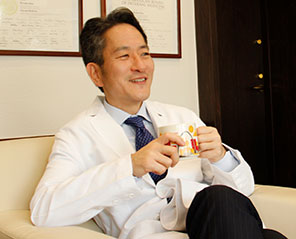◆職員にとっても安全な環境づくりを
―若い医師が安心して働ける環境づくりをライフワークにされていますが、具体的にはどのような取り組みをされているのですか?
私がちょうど研修医をしていた2001年ごろは医療訴訟が増え、医療へのバッシングも強い時代でした。過労から医療事故が起きたり、研修医が医療過誤で告訴される事例などもありました。恩師である森田茂穂先生から「若い医師が安心して働けるような環境を作るのがお前の仕事だ」と常々言われていたこともあり、アメリカ留学から帰国した後、取り組み始めました。
大事なのは、患者さんはもちろん、職員にとっても安全な環境をつくることです。人間だからミスをしてしまうことはありますが、患者さんに支障が出る事態につながらないシステム作りが必要です。
たとえば、起こりやすい医療事故の1つに、中心静脈にカテーテルを留置する手技があります。これを若手の医師が1人で行っていたり、あるいは1年目の初期研修医とほとんど実践したことのない3年目の医師の2人が組んでいたり……という実態があります。
そこで帰国後に赴任した板橋中央総合病院では件数をこなし、診療部長の承認を得た者だけが1人でこの手技を行うことができる認可制を導入しました。
また、インストラクター制度も取り入れています。これは、教える立場になるために必要な実績を定めたもの。当初は現場から反発もありましたが、患者さんの事故につながらないことが研修医を守ることにもなる、という話を丁寧に説明して少しずつ理解してもらいました。
―チーム医療も導入されたと伺いました。
1人の医師が全ての責任を持って1人の患者を診る主治医制は素晴らしいのですが、やはり人間の能力には限界があります。24時間365日となると難しい。そこで、きちんと申し送りをしてチームで診るという体制に変えていきました。ベテランの医師が常に入ることで、キャリアの浅い医師にとっても患者さんにとっても、良い影響が出ています。
こうした取り組みを、私たちのような民間病院が健全な経営の中で行うことに意味があります。国立でも大学病院でもない、補助金が全く出ない民間病院が身の丈に合った方法で実践すれば、他の病院でも可能だと示せるからです。もちろん簡単ではありませんが。
◆医療と法律の壁を超える医師に
―これまでのキャリアについてお聞かせください。研修医を終えた後、アメリカに留学されたのはどのような経緯からですか?
東京大学医学部を卒業するころに出会った森田茂穂先生に大きな影響を受けています。「世界のどこでも働ける地球人になれ」というのが口癖の森田先生は、アメリカに留学した麻酔科医の先駆けで、人間的にもとてもカリスマ性がありました。
当時、先生がいらっしゃった帝京大学医学部付属市原病院の麻酔科は「どんどん海外へ飛び出せ」という医局で、もともと国際協力に関心があった私は大いに魅力を感じ、研修医として入局しました。
入ってみると麻酔科は性に合い、非常に楽しかったです。というのも、麻酔科医は手術中の患者さんの代弁者として全身管理を行います。病気を直接治せなくても、バイタルを管理する、患者さんを死なせないという技術は、将来どんな医師になろうとも役に立つと感じました。
そして2001年、念願かなって、アメリカ・セントルイスにあるワシントン大学内科に留学することになりました。ワシントン大学へ行ったのは、最初に返事をもらった大学に留学を決めたからです。
―留学中にロースクールで弁護士資格を取得されたのはなぜですか?
実はそれについても、森田先生の影響です。さきほど研修医時代に医療訴訟が増えていた話をしましたが、国境だけではなく「医療と法律の壁を越えろ」「法律を勉強して、医者が安心して働けるような社会を作れ」というのも、森田先生からいつも言われていたことでした。私の顔を見て、研究者向きじゃないと感じたようです。
法律の知識を活かして医療環境を良くしたいという思いと、医療倫理について学んでみたい関心もあり、留学当初からロースクールに行くことは決めていましたね。
―弁護士資格を取得後のキャリアについて教えてください。
もともと日本へ帰国し、再び森田先生のもとで働こうと思っていたのですが、私が渡米後に森田先生が亡くなられたんです。それで帰国する理由がなくなってしまって――。どうしようか迷っていたところ、セントルイス退役軍人病院で新しくホスピタリスト科を立ち上げるので参加してみないかと誘われました。ちょうど2008年、ホスピタリスト(入院患者の内科管理を行う病院総合医)という言葉がアメリカで流行り始めたころです。
その病院には5年勤務していました。その間、アメリカ内には、経営的な理由でICUを立ち上げる病院が増えていました。私も必然的にICUに関わるようになったのですが、そこでまた新たな発見がありました。
というのは、これまでに経験してきた麻酔科と内科、法律の知識が全て活かせる分野が集中治療だと気付いたのです。「本気で集中治療をやってみよう」と思い、当時、集中治療で1番と評判だったピッツバーグ大学病院医学部集中治療科に行くことにしました。
約2年勤務した後でした。森田先生門下の兄弟子で、以前から「一緒に働こう」と声をかけてくださっていた新見能成先生のもとへ行くために帰国。2015年、板橋中央総合病院の副院長として着任しました。
◆適切な負荷や高度な平凡性…若手医師への思い
―2019年に院長に就任。現在はどのような点に課題を感じていますか?
板橋中央総合病院はもともと救急医療に力を入れているので、ともすると野戦病院のような様相を呈することもあるのです。しかし社会全体で働き方改革が叫ばれるようになり、医療業界でもそのような現場に厳しい見方も出てきています。
確かに、疲労した医師はミスをしやすいという考えも分かりますが、アメリカの医療現場を定期的に訪れている身としては、また少し違う気付きもあるのです。
アメリカでは今、研修医や若い医師の仕事環境が、労働時間を含めかなり整備されています。その結果、急変対応ができない医師が増えているのです。皆、カンファレンスなどでは難しい症例について意見を言えても、目の前の患者さんが「苦しい」と言ったとき、どうすればいいのか分からない。
環境を整えれば整えるほど、それを構成する人の成長は遅れるのでないか……と感じています。必要なのは、一律に負荷のない環境ではなく、本人の能力に合わせて、限界に近いぐらいの負荷をかけてでも任せる環境。実際、体力も気力もある若い人たちのポテンシャルを無駄にしてはいけないと思います。
―思い描く理想の教育像はどのようなものでしょうか?
先ほどもお話したように、まずは適切な負荷を意識すること。医師としての経験値を増やすためには、負荷を個別化して考えることが大切です。
次に高度な平凡性。たとえば集中治療の領域にも、心臓血管や外科などさまざまな専門医がいますが、皆がそういったスペシャリストでなくてもいいのです。それよりも持つべきは、適切な問診ができる、検査を解釈できる、患者さんの体を触って悪いところをきちんと発見できるといった“平凡な能力”。一見、簡単に思えるこうした能力こそが、専門医とコミュニケーションをとる際にもとても大事になってきます。
最後に、命より大切なものがあると知ってなお、命を大切にするということ。職業のプロフェッショナリズムもそうですが、命より大切にしたいものは、この世の中にきっとある。そのことについて考え、教え、そのうえでなお命を守る。そういう医師を育てたいと思っています。
日本とアメリカ、両方の良さを知っている自分だからこそ、最良のバランスでどう取り入れていくべきか。日々悩みつつ、柔軟に変化に対応しながら、理想の医療環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。
(インタビュー・coFFee doctors編集部)※掲載日:2021年12月23日